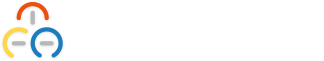仮想資産の監督、専門法制定へ 学者が2つの課題に注目
- 近年、国内の仮想資産監督が大きく進展しています。行政院は金融監督管理委員会(FSC)を仮想資産の主管機関に指定し、FSCはマネーロンダリング防止、原則の策定、自律規範の設置、業者の組合設立支援などを進めています。今年は専門法の制定を検討しており、学者は将来の仮想資産監督において詐欺と情報セキュリティの2つの課題に注目する必要があると指摘しています。
- 消費者基金会金融保険委員会の理事兼召集人であり、銘伝大学金融科技学院の副教授兼主任である林盟翔氏は、現在行政院がFSCを金融投資または支払い性質を持つ仮想資産の主管機関に指定することに問題はないと述べています。しかし、仮想資産自体の性質は固定されておらず、必ずしも金融用途に関与するとは限りません。証券性質を持つ仮想通貨(STO)は「技術+投資契約(Howey Test)」を採用し、投資性と流通性を持つ有価証券の定義に適合します。行政院が指定する金融投資性質には、STO以外に他の潜在的な金融商品があるのでしょうか?支払い性質の仮想資産はどのようなものでしょうか?FSCが監督範囲に含める可能性のある製品や業務について、業者や消費者が知ることができるメカニズムが必要であり、行政院の詐欺防止関連の施策や政策に協力するためにも重要です。
- 専門法を制定することで投資家保護が達成されるのでしょうか?林盟翔氏は、専門法や金融法規への組み入れだけが「消費者保護」への道ではないと指摘しています。新興技術の発展は日進月歩であり、動的な監督の制定は容易ではありません。FSCは国際的な監督措置を参考にし、マネーロンダリング防止を核心とした監督を行い、その後STOを証券取引法に組み入れ、昨年9月には指導原則を発表し、自律組織の設立を導いています。これらはすべて「消費者権益保護」を中心としています。技術の発展と革新を阻害しない理念に合わせて、「他律」(指導原則)と「自律」組織を組み合わせた「自下から上へ」(bottom-up)の二重軌道監督方式を採用し、現在の業者の経営現状に融合させ、その後他の法規の修正や専門法の推進を行います。
- 市場では、専門法の制定が仮想資産プラットフォームの将来の発展を阻害するのではないかと懸念されています。林盟翔氏は、「技術は中立であり、監督の観点から革新を阻害しないようにするため、技術自体とその応用対象の規範を分けるべきです」と述べています。仮想資産の使用においては、詐欺や情報セキュリティの懸念が増加しており、両者の差別化された監督が実施されていない認識が混乱を招いています。
- 彼は主管機関が産官学研の力を多く結集することを提案しています。例えば、Fintech Spaceを通じて新興技術業者を支援し、金融機関と協力して、金融科技発展ロードマップ2.0の計画の下で、監督技術と法令遵守技術の基盤から協力し、多様な試行や実験を通じて、仮想通貨取引のリスクや情報セキュリティの懸念を特定し、対応策を提案することができます。
- 林盟翔氏はまた、政府が将来仮想資産プラットフォームを監督する際に、詐欺と情報セキュリティの2つの課題に直面する可能性があると指摘しています。まず、詐欺については4つの点に注意が必要です。1つ目は、銀行を信託名義として利用し、消費者に金融機関または金融機関の保証があると誤解させること。2つ目は、仮想通貨の対面取引が詐欺や強盗のケースを引き起こすこと。3つ目は、出所不明のプラットフォームで取引を行い、金銭関連のパスワードやアカウントが漏洩し、仮想資産の取引が成功しないこと。4つ目は、投資実績や高収益を利用して、消費者に全く価値のないゴミコインを購入させることです。
- 情報セキュリティの面でも4つの点があります。1つ目は、管理、使用、監督の標準が確立されておらず、技術水準が一様でないため、監督の空白が生じること。2つ目は、プログラムやスマートコントラクトの出所が不明であり、技術に欠陥がある場合や意図的に誤りを生じさせることで、消費者の情報漏洩や権利の損害が発生すること。3つ目は、秘密鍵やパスワードの保存問題であり、以前は取引所が保管やホットウォレットサービスを提供していましたが、同様に盗難やハッキングの可能性